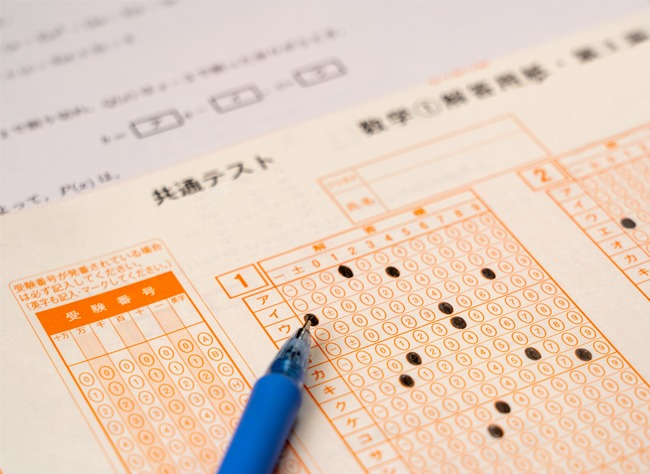【文系・難関国公立大特化】共通テストまで残り80日台!京大・阪大・神大合格者が実践した「超詳細」科目別・月別学習計画
目次
はじめに:残り80日台の現実と戦略
大学入学共通テストまで残り80日台。難関国公立大学(東大、京大、阪大、神戸大、一橋大など)を目指す文系受験生にとって、この時期は一年で最も過酷かつ戦略性が問われる「天王山」です。
特に京大・阪大・神大の志望者は、各々異なる戦略が求められます。
- 京大志望者: 「共テは足切り突破がメイン。二次の超難解な国語・英語・地歴論述に時間を割きたいが、共テで失敗もできない」
- 阪大・神大志望者: 「共通テストの配点比率が京大より高く、9割近くが目標。但二次の数学や英語、地歴論述(阪大)もハイレベル。どう両立すべきか」
受験生の悩み
- • 「共通テスト対策に振り切ったら、二次の論述の『勘』が鈍りそうで怖い」
- • 「地歴2科目のインプットが終わらず、焦りだけが募る」
- • 「理科基礎にいつから手を付ければいいのかわからない…」
この記事では、特に京大・阪大・神戸大の文系合格者が実践した「文系特化」の学習計画を、【合格者の声】や具体的な参考書名と共に、科目別に解説します。
全体戦略:文系・難関国公立大志望者のための「3フェーズ戦略」
残り80日台(約2ヶ月半)は、志望校の「共テ:二次」の配点比率を強く意識し、学習の比重を戦略的にシフトさせます。
フェーズ1:10月下旬~11月(残り80日~50日)
テーマ:二次論述力の維持 と 共テ未着手分野(地歴・理基礎)の完全インプット
共テ:二次 比率 = 5:5 ~ 6:4
(※京大志望者は 3:7 の場合が多い)
戦略と目的
この時期の最重要課題は、二次の得点源である英語(英作文・和文英訳)、数学(記述)、国語(記述)の論述力を維持することです。
それと並行し、共通テスト対策で最も時間がかかる「地歴・公民2科目」と「理科基礎2科目」の知識インプットを「完了」させる最終リミットです。12月から演習フェーズにスムーズに移行するため、この1ヶ月で知識の穴を徹底的に塞ぎます。
【合格者の声(京大法学部 Aさん)】
「11月時点では、京大の現代文記述と英語の和文英訳に8割の時間を割いていました。正直、共テは足切りさえ超えれば良いと割り切る気持ちもありましたが、失敗は許されない。そこで、知識で点が取れる『古文・漢文』『理科基礎』『地歴の未習分野』だけは、11月から毎日2時間確保してインプットを完了させました。京大志望者こそ、思考力が問われない分野で『絶対に落とさない』戦略が重要です。」
【合格者の声(神戸大経営学部 Cさん)】
「神戸大経営は数学の配点が高く、11月は二次の『文系の数学 重要事項完全習得編』の復習が中心でした。しかし、共テ模試で7割しか取れず焦り、11月下旬から毎日『IA・IIB』の共テ対策の時間を2時間確保しました。特に『データの分析』はゼロから詰め直しました。二次数学の思考力と、共テ数学の処理速度は全く別物だと痛感しました。」
フェーズ2:12月(残り50日~20日)
テーマ:共通テスト演習の最大化 と 二次論述の「感覚維持」
共テ:二次 比率 = 8:2 ~ 9:1
戦略と目的
学習時間の大部分を共通テスト対策に振り切ります。過去問に加え、主要予備校の実践問題集(例:河合塾『共通テスト総合問題集(黒本)』やZ会『共通テスト実践模試(緑本)』)を使い、演習量を確保します。
ただし、二次対策を「ゼロ」にはしません。週に数回(例:週末に3時間)は、志望校の「核」となる論述演習に触れ、「思考のエンジンを錆びつかせない」ことが極めて重要です。
【合格者の声(阪大外国語学部 Bさん)】
「阪大は共テの配点が高いので、11月は『日本史B一問一答(東進)』と論述対策の『考える日本史論述』を並行しました。共テ対策=二次対策の土台と捉え、12月から共テ過去問演習に入りましたが、間違えた選択肢は『なぜ間違いか』を説明できるレベルまで教科書を読み込みました。この『知識の精度を高める作業』が、そのまま二次の論述力に直結したと思います。」
フェーズ3:1月~直前期(残り20日~本番)
テーマ:知識の最終確認 と「本番シミュレーション」
共テ:二次 比率 = 10:0
戦略と目的
全受験生が共通テスト対策に集中します。新しい問題集には絶対に手を出せず、これまで解いた問題の復習、知識の総整理、体調管理に徹します。週末などを利用し、本番と同一の時間割(起床時間、試験開始時間、休憩時間)で予想問題パックを解く「リハーサル」を行い、脳と身体を本番モードに最適化します。
【科目別】超詳細・月別学習計画(文系特化)
英語【リーディング】
課題
二次試験で求められる「精読力(一文を深く訳す力)」と、共通テストで求められる「速読力(大量の情報を処理する力)」という、相反するスキルを両立させること。
10月下旬~11月
計画:
まず過去問を解き、80分の壁(膨大な語彙数と情報量)を体感します。自分がどの形式(グラフ、広告、長文意見)に時間をかかるかを徹底分析します。
二次との両立(最重要):
学習の中心は、京大・阪大・神大の二次対策(和訳・英作文・要約)に置きます。(例:『ポレポレ英文読解プロセス50』や『英文解釈の技術100』の復習、志望校の過去問演習)。
共テ対策への「接続」:
この二次対策で培った「共通テスト対策」に特化するというより、「二次記述対策」の読解力を維持・向上させることが中心です。京大・阪大志望者は、二次過去問(例:京大の第一問(評論文)・第二問(小説論述)、阪大の評論文記述)の演習を継続します。
【合格者の声(京大文学部 Dさん)】
「京大の現代文(特に傍線部説明)は、本文の要素を過不足なく抜き出し、論理的に再構成する訓練です。この訓練を積んでいたおかげで、共通テストの選択肢が『本文のどの要素が欠けているか』『どの要素が言い過ぎか』が瞬時にわかるようになりました。11月は二次対策(記述)に集中し、共テ(選択肢)は12月からで十分間に合いました。しかし、京大の小説論述と共テ小説は全く別物なので、共テ小説の『心情』問題のパターン(言動・情景描写から判断する)だけは別途演習しました。」
12月
計画:
予想問題集(『共通テスト総合問題集 国語(黒本)』(河合塾)など)を「読み物」として高速で通読します。用語を無理に暗記しようとせず、まずは「免疫とはどういう仕組みか」「ホルモンはどこから出て何をするか」という全体像(ストーリー)を掴みます。
1月(直前期)
計画:
過去問・模試で間違えた選択肢の「解答根拠」を再確認します。
英語【リスニング】
課題
京大・阪大・神大など、二次試験でリスニングが課されない大学の志望者が、最も対策を後回しにし、本番で「大事故」を起こしやすい最重要戦略科目。
【合格者の声(京大法学部 Aさん)】
「正直、11月までリスニングを完全に舐めていました。二次の英語と国語に追われ、『直前でいいや』と。12月の最後の共テ模試でリスニングの点数が4割で血の気が引きました。リスニングの『耳』は、1日休むと本当に鈍ります。そこから毎日30分、1.2倍速のシャドーイングを泣きながら続け、本番は何とか8割に乗せました。もっと早くからやるべきでした。」
【合格者の声(神戸大経営学部 Cさん)】
「神戸大経営は数学の配点が高く、11月は二次の『文系の数学 重要事項完全習得編』の復習が中心でした。しかし、共テ模試で7割しか取れず焦り、11月下旬から毎日『IA・IIB』の共テ対策の時間を2時間確保しました。特に『データの分析』はゼロから詰め直しました。二次数学の思考力と、共テ数学の処理速度は全く別物だと痛感しました。」
10月下旬~11月
計画:
毎日最低30分、共通テスト形式の音声(過去問・問題集)に触れる「義務化」します。これは勉強というより「筋トレ」です。
具体的な訓練:
ただ聞くだけでなく、「1.2倍速」でのシャドーイング(音声に続いて復唱する)やディクテーション(書き取り)を開始します。この高速音声に耳を慣らす作業が、本番の音声を「ゆっくり」感じさせるための鍵です。
二次との両立:
二次対策で疲れた日の夜、寝る前の30分を「リスニングタイム」としてルーティン化するのがおすすめです。
12月
計画:
予想問題集(例:『共通テスト実践模試(緑本)』(Z会)や『黒本』(河合塾))を週2~3回のペースで「時間厳守(70~75分)」で解く。
演習の質:
ただ解くだけでなく、選択肢がなぜ巧妙に作られているのか(例:本文の単語を使っているが内容は逆、一部は合っているが全体は間違い)、本文のどの部分のパラフレーズ(言い換え)なのかを徹底的に分析します。この「解答根拠の言語化」作業が、選択肢を吟味する精度を飛躍的に高めます。
二次との両立:
週1~2回、志望校の過去問(特に英語の和訳・英作文)を解き、「記述力」が鈍らないように維持します。
1月(直前期)
計画:
過去問(特に直近3年分)と、12月に解いた予想問題集の間違い直し。公式の最終確認。満点を狙うのではなく、「9割を堅く取る」という意識で、計算ミスをゼロにするための最終調整を行います。
数学(IA・IIB)
東大・京大・一橋大、そして阪大・神戸大(多くの学部)など、二次試験で数学が課される難関校志望者にとって、共通テスト数学は「絶対に失敗が許されない通過点」です。
10月下旬~11月
計画:
参考書(例:『文系の数学 重要事項完全習得編』や『スタンダード演習』)を...
共テ対策:
予想問題集(『共通テスト実践問題集(黒本)』(河合塾)や『大学入学共通テスト実戦問題集 数学(青本)』(駿台))を、本番と同じ時間(70分)で徹底的に演習します。難関大志望者は、共テの誘導に乗れず「考えすぎ」時間を失う罠に陥りがちです。「誘導に素直に乗る」練習と、「計算を最後まで合わせきる」訓練に集中します。
12月
計画:
予想問題集(『共通テスト実践問題集(黒本)』(河合塾)や『大学入学共通テスト実戦問題集 数学(青本)』(駿台))を、本番と同じ時間(70分)で徹底的に演習します。難関大志望者は、共テの誘導に乗れず「考えすぎ」時間を失う罠に陥りがちです。「誘導に素直に乗る」練習と、「計算を最後まで合わせきる」訓練に集中します。
1月(直前期)
計画:
過去問・予想問題集での演習を徹底的に行い、計算ミスを最小化し、知識の定着を図ります。
【国語】(科目別詳細)
二次試験(特に東大・京大・阪大)で記述力が問われるため、共通テストの「選択肢」対策との切り替えが重要です。
現代文(評論・小説)
10月下旬~11月
計画:
この時期の現代文は「共通テスト対策」に特化するというより、「二次記述対策」の読解力を維持・向上させることが中心です。京大・阪大志望者は、二次過去問(例:京大の第一問(評論文)・第二問(小説論述)、阪大の評論文記述)の演習を継続します。
共テ対策:
共通テストの過去問を解き、二次で培った「共通テスト対策」に特化するというより、「二次記述対策」の読解力を維持・向上させることが中心です。京大・阪大志望者は、二次過去問(例:京大の第一問(評論文)・第二問(小説論述)、阪大の評論文記述)の演習を継続します。
【合格者の声(京大文学部 Dさん)】
「京大の現代文(特に傍線部説明)は、本文の要素を過不足なく抜き出し、論理的に再構成する訓練です。この訓練を積んでいたおかげで、共通テストの選択肢が『本文のどの要素が欠けているか』『どの要素が言い過ぎか』が瞬時にわかるようになりました。11月は二次対策(記述)に集中し、共テ(選択肢)は12月からで十分間に合いました。しかし、京大の小説論述と共テ小説は全く別物なので、共テ小説の『心情』問題のパターン(言動・情景描写から判断する)だけは別途演習しました。」
12月
計画:
予想問題集(『共通テスト総合問題集 国語(黒本)』(河合塾)など)を使い、古文・漢文とセットで「100分」の時間配分の中で解く訓練を積みます。
1月(直前期)
計画:
予想問題集で間違えた選択肢の「解答根拠」を再確認します。
古文
10月下旬~11月
計画:
最優先かつ最重要課題は「古文単語」と「古典文法」の知識インプットの完了です。この時期にまだ助動詞(「る・らる」「す・さす・しむ」など)の接続や意味、敬語(尊敬・謙譲・丁寧)の使い分けが曖昧な場合、12月以降の演習は無意味です。
12月
計画:
予想問題集での演習を本格化。共通テスト特有の「和歌の解釈」「複数テキスト(本文と解説文)の読解」といった問題形式に慣れます。
1月(直前期)
計画:
古文単語帳の最終確認。特に「多義語」と「識別」の復習に集中します。
漢文
10月下旬~11月
計画:
漢文は、文系受験生にとって「最短で満点を狙える戦略科目」です。この1ヶ月で、「漢文句形(句法)」と「重要単語」のインプットを完璧にします。
12月
計画:
予想問題集の演習を本格化。漢文は時間をかけずに高得点を取る「得点源」です。「15分」という時間制限を設け、その中で確実に満点を取り切る訓練を積みます。
1月(直前期)
計画:
『早覚え速答法』などの句形帳を、試験当日まで毎日眺めます。
【最重要】地歴・公民(2科目選択)の詳細計画
文系受験生の共通テストの成否は、この2科目にかかっていると言っても過言ではありません。膨大な暗記量に加え、二次試験での論述対策も並行する必要があります。
日本史B 選択者
10月下旬~11月
計画:
「通史」のインプットを完了させる最終期限です。この時期にまだ教科書レベルの知識(例:摂関政治の流れ、江戸時代の三大改革)が曖昧な場合、12月以降の演習は無意味です。『金谷の日本史「なぜ」と「流れ」がわかる本(東進ブックス)』や教科書を高速で周回し、「流れ」と「因果関係」を完璧に理解します。
【合格者の声(阪大文学部 Eさん)】
「阪大は共テの配点が高いので、11月は『日本史B一問一答(東進)』と論述対策の『考える日本史論述』を並行しました。共テ対策=二次対策の土台と捉え、12月から共テ過去問演習に入りましたが、間違えた選択肢は『なぜ間違いか』を説明できるレベルまで教科書を読み込みました。この『知識の精度を高める作業』が、そのまま二次の論述力に直結したと思います。」
12月
計画:
過去問・予想問題集(『黒本』や『緑本』)の演習を本格化。共通テスト特有の「年代整序」「史料・図版問題」「正誤判定」の訓練を積みます。間違えた知識は、すべて一冊の参考書(または教科書)に「一元化」し、情報を書き込んでいきます。
1月(直前期)
計画:
一元化した参考書・ノートの高速復習。教科書、資料集の読み込み。特に文化史や戦後史など、直前まで詰め込める知識の最終確認を行います。
世界史B 選択者
10月下旬~11月
計画:
日本史同様、「通史」のインプット(特に近現代史)を完了させます。世界史は「横(同時代の別地域)」のつながりが重要です。『青木裕司 世界史B実況中継(語学春秋社)』や『神余のパノラマ世界史(学研)』などを使い、「19世紀ヨーロッパの動向」と「同時代のアジア(アヘン戦争など)」を関連付けて理解します。
12月
計画:
過去問・予想問題集の演習を本格化。年代整序、地図問題、史料問題の対策を重点的に行います。
1月(直前期)
計画:
一元化したノートや参考書、資料集の地図や系図の確認。特に近現代史と地域史を重点的に復習します。
地理B 選択者
10月下旬~11月
計画:
「系統地理」(気候、地形、農業、鉱工業、人口、都市など)の全分野における「理屈(因果関係)」を完璧にインプットします。
12月
計画:
過去問・予想問題集の演習を本格化させます。この演習の目的は、11月にインプットした「系統地理の理屈」を使って、初めて見る「統計データ」や「地誌問題」を解く訓練です。
1月(直前期)
計画:
演習で間違えた箇所の復習と、資料集の読み込みに徹します。
倫理、政治・経済 選択者
10月下旬~11月
計画:
「倫理分野(源流思想、西洋思想、東洋思想)」と「政治・経済分野(憲法、国際政治、経済理論)」の全範囲のインプットを完了させます。
12月
計画:
過去問・予想問題集を徹底的に行います。倫政は、演習(アウトプット)を通じて初めて知識が定着する科目です。共通テスト特有の「ひっかけ選択肢」の見抜き方(例:「すべて~」「~だけ」)を習得します。
1月(直前期)
計画:
一元化したノートや参考書、一問一答をひたすら高速で周回し、知識の最終確認を行います。
【理科基礎】(科目別・詳細改訂版)
文系受験生が後回しにしがちな「最大の穴」であり、同時に、短期間で9割以上を狙える「最大の戦略科目」です。ここで9割以上を2科目揃えられれば、共テ全体の得点が劇的に安定します。
11月からのゼロスタートでも全く問題ありません。重要なのは「科目選択」と「集中力」です。
【合格者の声(神戸大法学部 Fさん)】
「11月まで理科基礎はゼロでした。法学部の配点(共テ900点中100点)を見て、これは捨てられないと焦り、11月から『生物基礎』と『地学基礎』のインプット(『きめる!共通テスト』シリーズ)を毎日1時間半ずつ開始しました。12月はひたすら過去問演習。理科基礎は『知っているか知らないか』だけなので、やればやっただけ伸びました。この2科目で9割5分取れたことが、本番の精神的な余裕につながりました。」
【推奨】生物基礎(暗記中心・考察あり)
特性
文系受験生の多くが選択する王道科目。計算は「遺伝子(塩基の割合)」程度で、ほぼ暗記が中心。ただし、「実験考察問題」が出題されるため、単なる用語暗記では満点は狙えない。
10月下旬~11月(インプット完了期)
参考書(例:『きめる!共通テスト生物基礎』や『山川喜輝の生物基礎が面白いほどわかる本(KADOKawa)』)を「読み物」として高速で通読します。用語を無理に暗記しようとせず、まずは「免疫とはどういう仕組みか」「ホルモンはどこから出て何をするか」という全体像(ストーリー)を掴みます。
特に「免疫(獲得免疫の流れ)」「ホルモン(分泌器官と作用)」「生態系(バイオーム)」は最重要分野であり、混同しやすいため重点的に読み込みます。教科書の図やグラフも隅々まで確認します。
12月(演習+知識定着期)
過去問・予想問題集を「解く」のではなく「読む」ことから始めても構いません。問題と解説を読み、「何が、どのように問われるか」を知ることが先決です。
間違えた=知らなかった知識を、使っている参考書の一箇所に書き込み、一元化します。
「実験考察問題」は、一見難しそうでも、本文中に必ずヒント(対照実験など)があります。知識問題で時間を稼ぎ、考察問題に時間を充てる訓練をします。
1月(直前期)
一元化した参考書をひたすら高速周回。「免疫」「ホルモン」「遺伝子」など、混同しやすい分野は寝る前に必ず復習します。
【推奨】地学基礎(純粋暗記型)
特性
文系受験生の救世主。理科的な思考(計算や考察)が最も少なく、ほぼ純粋な暗記科目。物理・化学・生物の知識も不要で、完全に独立しています。11月からのスタートに最適です。
10月下旬~11月(インプット完了期)
参考書(例:『きめる!共通テスト地学基礎』)を読み込み、「固体地球(岩石、プレート)」「大気と海洋」「宇宙」の3分野の用語を暗記します。
特に「岩石(火成岩・堆積岩・変成岩)の分類」や「天体(惑星・恒星)の分類」は、理屈抜きで暗記が必要です。資料集の図やグラフとセットで覚えると効率的です。
12月(演習+知識定着期)
生物基礎と同様、過去問・予想問題集で「問われ方」を知り、知識の穴を埋める作業を繰り返します。計算問題は「地震(P波S波の到着時間)」程度しかなく、パターンも決まっているため確実に得点源にします。
1月(直前期)
計算パターンと、暗記事項(特に無機物質)の最終確認。
【注意】化学基礎(計算+暗記型)
特性
計算と暗記がバランス良く出題。「モル計算」「中和滴定」「酸化還元」といった計算で差がつきます。暗記量は生物・地学より少ないですが、計算アレルギーがある文系受験生は避けるべきです。
10月下旬~11月(インプット完了期)
まずは「暗記事項」(炎色反応、沈殿の色、無機物質)を終わらせます。
同時に、最重要の「モル計算(mol/L, g/mol)」と「中和滴定の計算パターン」だけを、薄い問題集(例:『宇宙一わかりやすい化学基礎(学研)』)で徹底的にマスターします。
12月(演習期)
過去問・予想問題集を徹底的に行います。計算問題に時間をかけすぎないよう、知識問題(暗記)を先に解き切る訓練をします。
1月(直前期)
計算パターンと、暗記事項(特に無機物質)の最終確認。
【注意】物理基礎(思考・公式型)
特性
「暗記が大嫌い」で「数学が得意」な文系受験生にとっては、暗記量が最も少なく、理屈で解けるため「隠れた得点源」になります。しかし、数学的思考が苦手な受験生が手を出すと、公式の意味が理解できず壊滅するリスクがあります。
10月下旬~11月(インプット完了期)
参考書(例:『宇宙一わかりやすい物理基礎(学研)』)を読み、「力学(運動方程式、エネルギー保存)」「熱力学」「波動」「電磁気」の基本公式とその「意味」を理解します。
12月(演習期)
過去問・予想問題集を解き、公式を使いこなす訓練を積みます。
1月(直前期)
すべての公式とその適用条件を最終確認します。
結論:あなただけの「合格戦略」は、まだ間に合う
この記事で、共通テストまでの大まかな戦略と学習計画はわかった。
「でも、京大志望の自分は、12月の共テと二次のバランスを具体的にどうすればいいんだろう…」
「今の自分の成績(最後の模試)から、本当に阪大・神大に間に合うのか不安だ…」
そんな不安を抱える京大・阪大・神戸大、その他の難関国公立大を目指す文系受験生のために。
私たち現論会 大阪梅田校・四条烏丸校は、そんな「直前期」の受験生こそ、最後まで全力で寄り添います。
「今からじゃ遅いかも…」そんな不安がある方こそ、「直前期でもOK!無料相談」にお越しください。
あなたの現状(模試の結果、得意・不得意、志望校)を詳細に分析し、志望校合格までの最短ルートを示す「あなただけの共通テスト科目別ロードマップ」を、面談で一緒に作成し、その場でプレゼントします。
残り80日台。ここからの1日1日の密度が、あなたの未来を決めます。一人で抱え込まず、まずはその不安を私たちにぶつけてください。